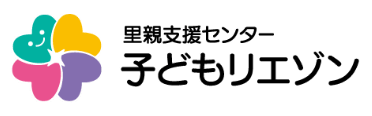街の書店
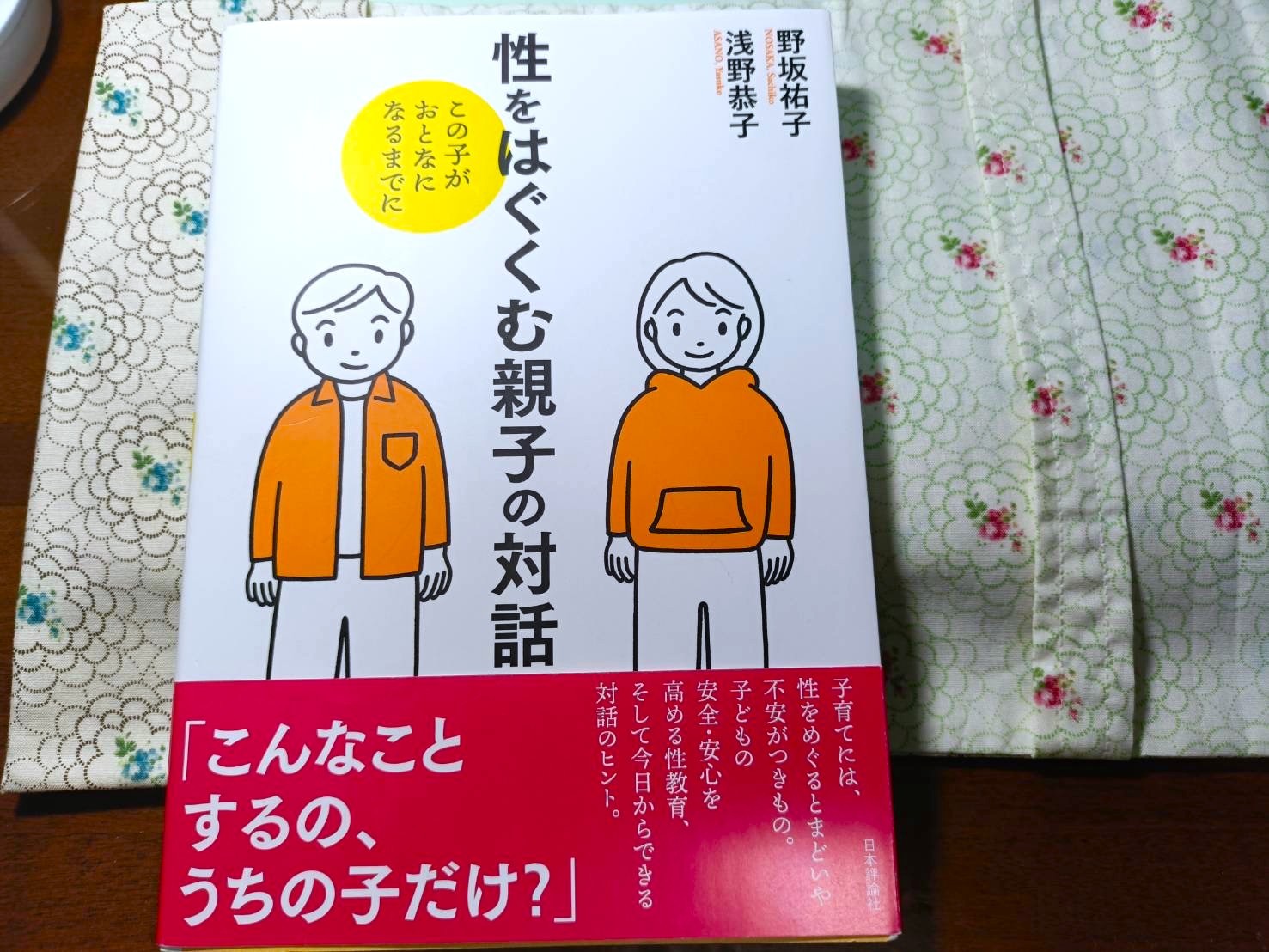
寒波に見舞われた成人の日祝日の三連休、いかがお過ごしでしたか。連休中日の朝、私は普段通りラジオを聞きながら家事をしていると、「愛媛県松山市」と聞こえたので手を止めてラジオに耳を傾けました。
NHKラジオ「著者からの手紙」で、小島俊一さんの著書『2028年 街から書店が消える日 』について話をされていました。小島さんは松山市の書店に出向されて経営を立て直された方です。V字回復をした原動力として小島さんは「大手書店と差別化するには人しかない。従業員のやる気、そのために、従業員研修を充実させた。研修をするということは「あなたを大事にします」ということ。そして、権限移譲をした。本が好きだから集まっている。好きなようにやらせた。従業員の満足なくして、顧客の満足はない。」書店に限らず、福祉の事業でも同じことが言えるのではと頷きました。
私は学生時代だけでなく、社会人になってもずっと通勤や生活にバスを利用していましたので、バスの待ち時間が15分あれば、近くの書店へ行くのが楽しみでした。「書店に立ち寄ると、あなたを向上させる何かがある」その書店のいたるところで目にした言葉です。本を開くことで、新しい情報に触れ。知識を広げたり深めたりすることができました。当時は、本から得る情報が一番多かったと思います。
今年こそは、本を開く時間を増やしていきたい。ちょうど手元には昨年の夏から秋に数回講演を聞く機会に恵まれた野坂祐子さんの本があります。野坂さんは、大阪大学大学院人間科学研究科教授で社会的養育の子どもや支援者に関わる活動に深く関わり、そこから本をたくさん書かれています。私は多忙を理由にこの本を斜め読みして閉じていたので、もう一度読み返してみます。休日には本を読んで充電して、また、日々の活動に繋げていければと思います。
(石丸)
【次回:しりとり】
【前回:巳年 へびいちのすけ】